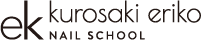ネイル業界トピックス/ 黒崎えり子ネイルスクール(新宿・名古屋・大阪梅田・横浜)
取れないネイルチップの付け方・外し方とは?爪を傷めない方法(両面テープ・グルー・ジェル・粘着グミ) - 黒崎えり子ネイルスクール(新宿・名古屋・大阪梅田・横浜)

「自宅で手軽にネイルできたらよいのに」と考えている方におすすめなのが、ネイルチップです。ネイルチップはすでに完成された素材を自爪に付けることで、簡単に指先をおしゃれに仕上げることができます。
そこで今回はネイルチップの魅力をはじめ、両面テープ、ネイルグルー・ジェル、粘着グミを使用するメリット・デメリット、取れにくくする付け方をご紹介します。また、爪を傷めないためのネイルチップの外し方もまとめているので、ぜひご参考にしてください。
まずは押さえておこう!ネイルチップの3つの魅力
ネイルチップとは、爪型をした透明のチップ(素材)にジェルやマニキュアを塗ってデザインを施した付け爪のことです。すでに完成されたものを購入すれば本格的なネイルを楽しめますし、自作することもできます。そこで、以下ではそんなネイルチップの魅力を3つご紹介します。
ネイルチップは、爪のおしゃれを手軽で簡単に楽しめるアイテムです。「仕事の関係でネイルができない」「ネイルサロンに足を運ぶ時間がない」という方であっても、ネイルチップを装着すれば爪を一気におしゃれにすることができます。
さらに、結婚式やデートなどの特別なシーンでは華やかなデザイン、翌日友達とのお出かけのときにはシンプルなデザインといったようにその日の気分やファッションに合わせて付け替えて楽しむことも可能です。ネイルチップがあれば爪のおしゃれに困ることがなく、かつアクセサリー感覚で楽しめるのは最大の魅力といえるでしょう。
爪の形の悩みを解消できる
爪の形は人によって異なるため、悩みを抱えている方は少なくありません。たとえば、爪の形が全体的に小さく横に広がっていると「ネイルをしてもきれいに見えない」ということも。その点、ネイルチップは好みの形や長さを選ぶことができます。自爪をカバーして理想とする爪の形に仕上げることができるので、悩みを解消し指元のおしゃれを楽しむことが可能です。
コスパに優れている
ネイルチップは、コスパに優れているのも魅力のひとつです。一度使用したネイルチップであっても、きれいな状態で保管しておけば何度でも繰り返し使うことができます。そのため、ネイルをするたびに都度購入する必要がないので、費用を抑えて指元のおしゃれが楽しめます。
ネイルチップを装着する前にやっておくべき下準備

ネイルチップを長持ちさせるためにも、まずは以下の下準備をしっかり行うようにしましょう。
ネイルチップの形を調整する
ネイルチップをきれいに装着するためには、まずは形を調整しましょう。
自爪にフィットするよう、チップの横幅や根元のカーブを確認。もし横幅が合わない場合は、少し大きめのチップを選び、ネイルファイルで自爪の形に合わせて削るのがおすすめです。爪の根元部分のカーブと横幅を合わせることができれば、ネイルチップが浮いて外れにくくなるだけでなく、まるで自爪のような仕上がりにできます。
なお、既存のチップの中に自爪にぴったり合うものがあれば、無理に削らずそのまま使ってOK。サイズやカーブがしっくりくるかどうかを確認してみてください。
自爪の長さや形を整える
自爪の長さや形を整えておくことも重要。
ネイルファイルを使い、自爪はチップよりやや短めに整えるのがポイントです。なお、二枚爪を防ぐためにもファイルは往復せず一方向に動かすようにしましょう。
爪の汚れ・油分を除去する
自爪に汚れ・油分が付着しているとネイルチップを装着した際に外れやすくなってしまいます。そのため、ネイルチップの装着前に石鹸で手を洗い、しっかり水気を拭き取るようにしましょう。爪を乾かしたらアルコールを使って、爪の表面の油分を拭き取ります。これで下準備は完了です。
両面テープを使ったネイルチップの付け方・外し方

ネイルチップを初めて使う人や、手軽にネイルを楽しみたい人に人気なのが、両面テープを使ったネイルチップの使用。両面テープはネイルグルーと比べて付け外しが簡単で、扱いやすいのが最大のメリットです。100円ショップでも手に入るため、コスト面でも優れており、使用後にきれいに剥がせばネイルチップを繰り返し使うことも可能です。
一方で、粘着力はやや弱めなので、激しく手を使ったり、水に触れる機会が多かったりするとチップが外れてしまうことも。粘着力が心配な方は、予備の両面テープを持ち歩くのがおすすめです。
ここからは、両面テープを使ったネイルチップの基本的な付け方と外し方を紹介します。
両面テープを使ったネイルチップの付け方
では、ネイルチップはどのようにして付ければよいのでしょうか。以下では、両面テープを使った付け方をご紹介します。
ネイルチップに両面テープを貼る
まず、ネイルチップの裏面の根元に両面テープを貼り付けます。このとき、両面テープがネイルチップからはみ出てしまったらカットしましょう。
「ネイルチップの密着をさらに持続させたい」という場合は、両面テープを半分にカットして貼り付ける方法もあります。半分にカットした両面テープをネイルチップの端に合わせて貼り付けることで、横に隙間ができてしまうのを防ぐことが可能です。これにより、隙間からのホコリの侵入を防ぎ両面テープの粘着力を維持することができます。
自爪にネイルチップを乗せて押さえる
次に、自爪にネイルチップを乗せます。このとき、根元からカーブに合わせて貼っていくことできれいに貼り付けることが可能です。ネイルチップを爪全体に合わせたら空気を抜きながら押し、密着させていけば完了です。
両面テープを使った際のネイルチップの外し方
ネイルチップは、正しい外し方を覚えておかないと爪を傷めてしまう恐れがあります。そのため、以下にて爪を傷めないネイルチップの外し方を押さえておきましょう。
両面テープなので「そのまま剥がしてもよいのでは?」と考える方もいますが、無理に剥がすのは望ましくありません。なぜなら、爪は3層構造でできており無理に剥がすと爪の表面の層まで剥がれてしまうからです。そのため、両面テープを使用した際はまず粘着力を弱める必要があるのでお湯を使用します。
お湯を溜めた容器に指先を入れ、1〜2分程度待ちます。両面テープの粘着力が弱まると自爪とネイルチップの間に隙間ができるので、そこにウッドスティックや爪楊枝を差し込み丁寧に剥がしていきます。仮に、1回で剥がれない場合は再度お湯に指先を浸けて、両面テープをふやかしてから行うようにしましょう。
ネイルグルー(接着剤)やジェルを使ったネイルチップの付け方・外し方

よりしっかりとネイルチップを固定したい人におすすめなのが、ネイルグルー(接着剤)やジェルを使った装着方法。両面テープに比べて粘着力が高く、多少の衝撃や水に触れても外れにくいため、長時間つけていたいときにぴったりです。外出先で付け直す必要もほとんどないので、安心して過ごすことができます。
ただし、しっかり装着できる分、オフには専用のリムーバーや手間が必要。無理に剥がすと自爪を傷めるリスクがあるため、丁寧に扱わなければいけません。また、リムーバーによってネイルチップが溶けてしまうこともあるため、繰り返し使いたい人にはやや不向きといえるでしょう。
ここからは、ネイルグルーやジェルを使ったネイルチップの付け方・外し方を紹介します。
ネイルグルー(接着剤)やジェルを使ったネイルチップの付け方
続いて、ネイルグルーを使った付け方をご紹介します。
ネイルグルーを爪に塗布する
まず、ネイルグルーを少量取って爪に塗っていきます。ネイルグルーの量が多いとネイルチップを装着した際にはみ出してきてしまうので、少量ずつ塗っていくのがポイントです。
ネイルチップを置く
ネイルグルーを塗り終わったら、根元のカーブに合わせながらネイルチップを自爪の上に置きます。このとき、両面テープを使った付け方と同様に空気が入らないように注意しましょう。
ネイルグルーを乾かす
ネイルグルーがはみ出した場合は、コットンまたはキッチンペーパーを使って拭き取ります。あとは、1〜2分程度待ったらネイルグルーが乾くのでこれで完成です。
ネイルグルー(接着剤)を使った際のネイルチップの外し方
ネイルグルーを使用した際は、専用のリムーバーを使ってネイルチップを外していきます。
まず、ネイルチップの隙間にリムーバーを垂らし、1〜2分浸透するのを待ちます。次に、ウッドスティックや爪楊枝を隙間に差し込んで丁寧に剥がしていきます。仮に、剥がれにくい場合は無理に剥がそうとしてはいけません。再度リムーバーを浸透させてからネイルチップを外すようにしましょう。
爪の表面に残ったネイルグルーは、コットンやキッチンペーパーにリムーバーを含ませて落としていきます。落ちにくい場合はネイルファイルで表面を磨いて落としていきましょう。
粘着グミを使ったネイルチップの付け方・外し方

ネイルチップ専用の接着剤のひとつである「接着グミ」。ぷにぷにとした弾力のある質感が特徴で、しっかり固定しながらも簡単に取り外せるのが魅力です。うまく使えば、粘着グミを剥がしてチップを再利用することもできるため、コスパ面でも優秀。
ただし、水(特にお湯)には弱く粘着力が低下しやすいため、手洗いや入浴時には注意が必要です。粘着力が心配な人は、予備の粘着グミを用意しておくと安心でしょう。
ここからは、粘着グミを使ったネイルチップの付け方と外し方の手順を紹介します。
粘着グミを使ったネイルチップの付け方
ネイルチップの装着は、たった2ステップ。初心者でも簡単にできるため、ぜひ挑戦してみてください。
ネイルチップに粘着グミを貼る
まずは台紙に貼り付けられている粘着グミを剥がし、ネイルチップの裏側に貼り付けます。
チップの根元に合わせて貼り付けることで、装着したときのフィット感がぐっとアップします。
自爪にネイルチップを乗せて押さえる
粘着グミを貼ったネイルチップを、自爪の上に乗せ、しっかり押さえます。
チップ全体が自爪にフィットするよう、軽く圧をかけながら押さえて固定しましょう。
粘着グミを使った際のネイルチップの外し方
ネイルチップの爪先をつまみ、指先の方向へやさしく引っ張ります。爪先に力を加えるようにすると、チップの根元が浮きやすくなり、スムーズに外すことができます。
チップを外したあと、ネイルチップ側に粘着グミが残っている場合は、お湯で温めると外しやすくなっておすすめ。粘着力が強いと感じたときは、チップをつけたまま指先をお湯につけてから外すと、負担をかけずに取り外せます。
また、自爪側に粘着グミが少し残ってしまった場合は、リムーバーを使ってやさしく拭き取ると、きれいに仕上がりますよ。
ネイルチップを外した後のアフターケア方法
ネイルチップを外したあとは、爪や指先のケアも忘れずに行いましょう。
キューティクルオイルや爪専用の美容液を塗り、爪の表面をしっかりと保湿するのがポイント。爪専用のアイテムが手元にない場合は、ハンドクリームでも代用可能です。
指でやさしくマッサージしながらなじませることで、より効果的に潤いを与えることができます。
よくある質問
ネイルチップについたのりやシールはどうやって取ったらいいですか?
ネイルチップについたのりやシールの外し方は、ぬるま湯に浸けて粘着力を弱めて取り除くのが一般的。
ウッドスティックに水を含ませたコットンを巻きつけて、少しずつ押しながら取り除く方法もおすすめです。
ネイルチップは粘土ジェル(クレイジェル)でも付けられる?外し方は?
粘土ジェル(クレイジェル)でもネイルチップを付けることは可能です。
流れにくく、隙間をしっかり埋めて固定できるため、安定感のある仕上がりになります。
外すときは、ネイルグルー(接着剤)やジェルを使った場合と同じ方法で問題ありません。
ネイルチップで長さ出しした場合の外し方(オフ方法)は?
まずは、長さ出しに使ったチップ部分をニッパーやネイルファイルで短くカットします。
次に、通常のジェルネイルと同様にオフしますが、ソフトジェルとハードジェルで落とし方が異なる点に注意しましょう。
また、チップ自体はアセトンでは溶けないため、再利用が可能。
再利用したい場合はチップをカットせず、表面に残っているジェルやグルーを取り除いてから外すのがおすすめです。
まとめ
ネイルチップは、手軽で簡単に指先をおしゃれにできる便利なアイテムです。「ネイルをしたいけれどできない」という方であっても取り入れやすいので、日々のおしゃれを楽しむことができます。ただし、ネイルチップを使用する際は正しい付け方と外し方を覚えておかなければなりません。今回ご紹介した内容を参考に、ぜひ試してみてください。