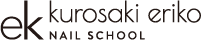ネイル業界トピックス/ 黒崎えり子ネイルスクール(新宿・名古屋・大阪梅田・横浜)
ネイルサロンの開業に必要な資格や資金!開業までの基本的な流れをチェック - 黒崎えり子ネイルスクール(新宿・名古屋・大阪梅田・横浜)

「自分の理想が詰まったネイルサロンを開業したい」と夢見ているネイリストの方は少なくないはず。しかし、実際に開業するとなると「開業するために必要な資格はあるの?」「開業にはどれくらいの資金が必要になるの?」などさまざまな疑問を抱くことでしょう。
そこで今回は、ネイルサロンの開業にあたって取得しておいたほうがよい資格や必要な資金、開業までの基本的な流れ、開業届などについてご紹介します。ネイリストとしてさらに活躍するために独立開業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
ネイルサロンの開業に資格は必要?持っておきたい資格・スキルとは?
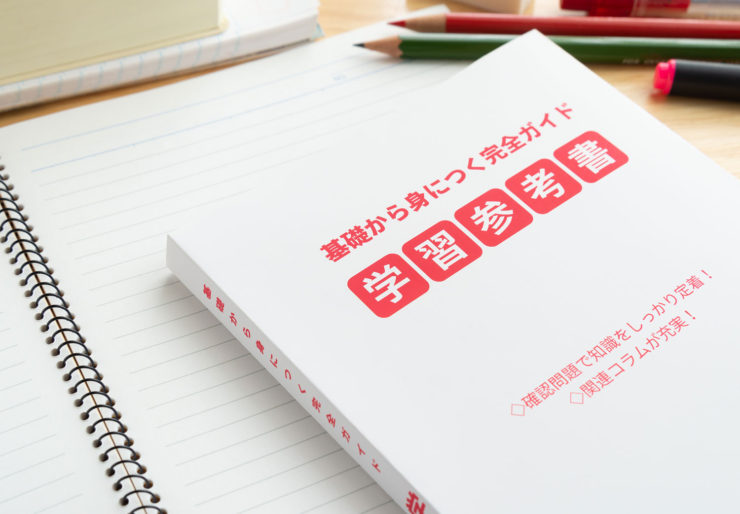
ネイリストは国家資格ではないため、ネイルサロンを経営するにあたっての必要な資格はとくにありません。しかし、お客さまの爪や指先に施術をする仕事なので、専門的な知識や技術は不可欠です。ひとりのネイリストとして確立するためにも、そしてお客さまに安心して利用してもらえるネイルサロンにするためにも、資格は積極的に取得するようにしましょう。
なお、ネイルサロンは厚生労働省が定めた「衛生管理に関する指針」を踏まえた上で店舗づくりを進める必要があります。資格は必要ありませんが、こうした衛生管理の徹底は勧告されているため、きちんと理解しておくことが大切です。
参照:厚生労働省「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について」
取得しておきたい資格
ネイルに関する資格は「必ず取得しておかなければならない」というわけではありませんが、資格を取得していればネイリストとしての信頼度は高くなるといえるでしょう。ネイリストが保有している資格をチェックしてサロン選びをする方もいるため、以下でご紹介する資格はなるべく取得しておくことをおすすめします。
JNECネイリスト技能検定試験
「JNECネイリスト技能検定試験」は、公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター(JNEC)が主催する資格試験です。1997年から実施されており、日本のネイリスト資格のなかで最も歴史と実績のある試験といわれています。
試験内容は筆記と実技で、3級〜1級まで用意されています。ニッパーやプッシャーなどの道具の扱いも試験の結果に関係してくるため、日々の練習が合否をわけます。
サロンワークを行うには2級以上の知識・技術が必要とされているので、サロン開業を目指す方は自分の力を試すために試験に挑戦してみるのもよいでしょう。
なお、ネイルサロンの求人では「JNECネイリスト技能検定の有資格者を優遇」としているケースもあります。その点からも、ネイル業界ではプラスに受け止められる資格だといえるでしょう。
| 受験資格 | 資格の特徴 | |
|---|---|---|
| 3級 | 義務教育を修了 | ネイリストに最低限必要なネイルケアやネイルアートの基礎的な知識・スキルを有している |
| 2級 | 3級の資格取得者 | サロンワークに必要なネイルケア・リペア・チップ&ラップ、ネイルアートの知識・スキルを有している |
| 1級 | 2級の資格取得者 | ネイリストとしてのトップレベルの知識・技術を有している |
参照:公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター(JNEC)
JNAジェルネイル技能検定試験
「JNAジェルネイル技能検定試験」は、NPO法人日本ネイリスト協会が主催する資格試験で、合格するとジェルネイルの知識と技術を習得したという証になります。
試験内容は筆記と実技で、初級・中級・上級の3つのランクが用意されています。初級の実技ではポリッシュの技術力も見られるため、ジェルネイル以外のネイル技術も磨きましょう。
なお、サロンワークを行うには中級以上の知識・技術が必要とされています。
| 受験資格 | 資格の特徴 | |
|---|---|---|
| 初級 | 義務教育を修了 | カラーリングやアートなどの、ジェルネイル施術の基礎的な知識・スキルを有している |
| 中級 | 初級の資格取得者 | ジェルオフやグラデーションなどの、サロンワークの専門的な知識・スキルを有している |
| 上級 | 中級の資格取得者 | デザインやスカルプチュア、ジェルチップなどの、ジェルネイルスペシャリストの知識・スキルを有している |
JNAネイルサロン衛生管理士
「ネイルサロン衛生管理士」も取得しておきたい資格のひとつです。合格すれば、より衛生面に配慮されたネイルサービスを提供できるようになるため、お客さまに安心感を届けることができます。
試験内容は講習と筆記で、18歳以上であれば誰でも受講可能です。ネイルサロンでの実務経験が問われることはないため、ネイリストを目指している方や、ネイルサロンの開業を目指している方も挑戦しやすい資格といえます。
習得しておきたいスキル
ネイルサロンを開業するなら、以下のスキルは習得しておきましょう。
ネイルに関する技術と知識
ネイリストとして独立して開業するなら、ネイルに関する技術と知識は必須といえます。リピーターをつくるためにはある程度の技術と知識が求められるため、技術と知識の習得はとくに意識するとよいでしょう。ネイル分野はトレンドのデザインや新しい技術が次々に生まれているため、開業後も技術と知識を身につけ続けることが大切です。
コミュニケーション能力
ネイリストにはコミュニケーション能力も必須です。コミュニケーション能力が高くないとお客さまの希望をヒアリングすることができないだけでなく、ネイリストとの会話を楽しみにして来店されるお客さまのニーズに応えることができません。お客さまの希望のデザインを叶えたり、お客さまに似合うデザインを提案したりするためにも、コミュニケーション能力は高めておきましょう。
ネイルサロンの開業にはどれくらいの資金がかかる?

では実際に、ネイルサロンの開業にどれくらいの資金がかかるのかを見ていきましょう。
自宅開業の場合とテナント開業の場合に分けてご紹介します。
自宅開業の場合
自宅開業する場合に必要となる資金の目安は以下の通りです。
|
項目 |
費用の目安 |
|---|---|
|
内装費用 |
約5~100万円 |
|
看板設置費用(設置する場合) |
約20~40万円 |
|
家具類の購入費用 |
約10~30万円 |
|
施術に必要な備品代 |
約20~30万円 |
|
広告宣伝費用 |
約5~50万円 |
自宅開業は比較的費用が抑えられる開業方法です。しかし、店舗と自宅の入口を分ける場合や間取り変更を行う必要がある場合、看板設置を行う場合は費用がかかります。
テナント開業の場合
テナント開業をする場合に必要となる資金の目安は以下の通りです。
|
項目 |
費用の目安 |
|---|---|
|
物件取得費用(敷金・礼金・保証金含む) |
約50~100万円 |
|
改装費用(内装・外装) |
約200~1,000万円 |
|
家具類の購入費用 |
約10~30万円 |
|
施術に必要な備品代 |
約20~30万円 |
|
広告宣伝費用 |
約5~50万円 |
テナント開業をする場合は、店舗の立地や広さなどにより異なります。物件取得費用や家具類・施術に必要な備品類の購入費用を抑えるのは難しいですが、内外装の費用は居抜き物件が見つかれば、広告宣伝費用はSNSを駆使することによって抑えることができるでしょう。
一方、取得した物件が広い場合やそもそもの賃料が高い場合、内外装にこだわる場合は費用が高額になる可能性があります。
ネイルサロン開業までの基本的な流れ

ネイルサロンを開業する際は、基本的に以下のような流れとなります。開業にあたってやることがたくさんあるため、ある程度の流れを覚えておくとよいでしょう。
オープン日や開業形態を決める
最初にオープン日を決めておくと開業準備がスムーズに進みます。自宅サロンなら3ヶ月、スタッフを雇う場合や内装工事を行う場合は半年が目安です。内装業者などが決まり次第、業者側にも共有しておくことをおすすめします。
物件を決める
物件が決まらなければ開業準備が進みません。まずはネイルサロンの開業場所を大まかに決めて、条件に合う物件があるか探してみましょう。物件が決まったら水道や電気なども開設しておきます。
電話開通
予約の電話やインターネットの使用に必要となるのが電話です。電話の開通工事はすぐに予約が取れないこともあるので、早めに対応しておきましょう。
求人募集
スタッフを雇う予定なら、物件が決まったあとすぐに求人を出しましょう。求めている人材を集めるにはある程度日数が必要になります。スタッフが決まったら、早めに研修のスケジュールを組むとよいかもしれません。
設備の搬入
内装工事が終わり次第すぐに設備を搬入できるよう、ネイルサロンの開業に必要な用具、用材や設備をある程度決めておきましょう。このとき、サロンのイメージやコンセプトに合ったものを選ぶことが大切です。
店舗の規模やコンセプト、こだわりの施術内容などによって揃えるべき道具や機材は異なります。いざ開店してから買い忘れに気づいた!ということにならないよう、早めに必要なものをピックアップしましょう。
SNSの開設
ある程度準備が整ったら、SNSも開設しましょう。オープン日を宣伝して集客につなげたり、得意とするデザインやサロンまでの地図などを載せておいたりするとよいかもしれません。このほか、施術メニューや施術の様子、ネイルケアに関する豆知識、今季おすすめのカラー・デザインなどをアップすることで、興味を持ってくれた方が来店してくれる可能性も出てきます。複数のSNSを活用することで、幅広い年齢層の方にアプローチできるでしょう。
オープン準備
すべての準備が整ったら、ようやくオープン準備に取り掛かります。カラー見本やデザインサンプルも用意しておきましょう。スムーズに施術できるかプレオープンを行うのも一案です。
ネイルサロンの開業に届け出の提出は必要か?

ネイルサロンを開業し利益を得るのであれば、「開業届」の提出が必要になります。これは税務署に提出する届出で、「これから所得が発生すること」を申告するために用います。
日本国民には納税の義務があるため、一定以上の収入が見込まれる場合、納税のための手続きが必要です。ネイルサロンを本業として経営する場合は年間38万円以上、副業として経営する場合は年間20万円以上の収入があるならば、開業届を提出するようにしましょう。
なお、詳細については、国税庁のサイトをご覧ください。
ネイルサロンを開業したら開業届は必要?
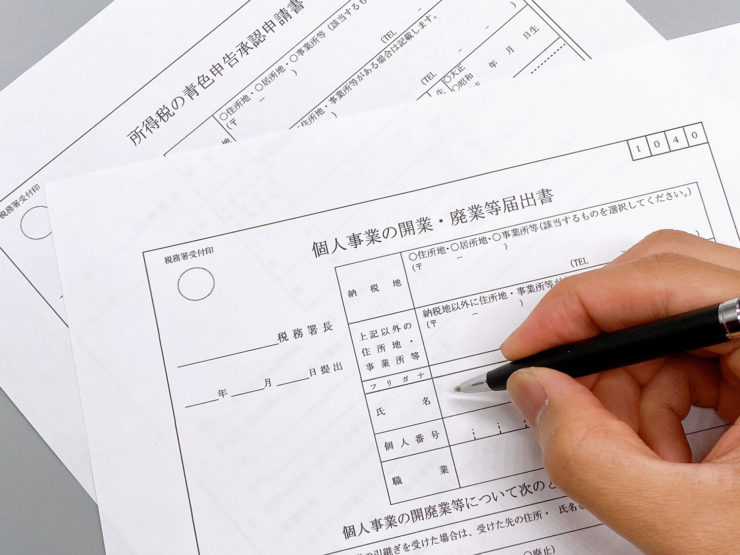
ネイルサロン開業の場合、美容室やエステサロンとは異なり保健所への開業申請は必須ではありませんが、開業することで個人事業主となるため、税務署への「開業届」を提出する必要があります。開業届は開業から1ヶ月以内に屋号(店舗名など)を記載して提出しなくてはならないため、開業準備と一緒に屋号を決めておきましょう。
個人事業主としてネイルサロンを開業すると、毎年確定申告を行うことになります。確定申告には白色と青色があり、特別控除が受けられて節税効果が高いのは青色申告となっています。特別控除が受けられれば、最大65万円の控除が適用されるため、ネイルサロンを経営していく上でかなりお得です。この青色申告を行うためには、開業届の提出と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する必要があるため、忘れずに提出しましょう。
なかには「開業当初は売上が少ないから…」「空いている時間にやるだけだから…」と開業届の提出や確定申告を怠る方もいます。しかし、いくら利益が少なくても「サービスを提供してお金をいただく」というのは立派な開業方法のひとつです。税務署への開業届提出や確定申告を怠ると、開業がバレた際に過去の分まで納税を迫られる可能性があるため注意してください。
ちなみに、開業届の提出時には「開業届」「青色申告承認申請書」「本人確認書類(運転免許証など)」「マイナンバーカード」「印鑑(認印可)」の5つが必要となります。開業届の書類は国税庁のホームページからダウンロード可能です。
まとめ

ネイリストは国家資格ではないため、開業にあたって取得しなければならない資格は存在しません。しかし、独立開業となるとお客さまの信頼を得る必要があるため、ある程度の資格は取得しておいたほうがよいでしょう。今回ご紹介した資格やスキル、必要な資金、開業までの主な流れを参考に、ぜひ独立開業の夢を実現させましょう。さらに、開業届・青色申告承認申請書の提出も忘れずに行ってください。
なお、家事や子育てで忙しいからこそネイルサロン開業を考えているという方は、以下のページをご覧ください。黒崎えり子ネイルスクールが提供しているネイルサロン開業サポートの6ステップについてご紹介しています。